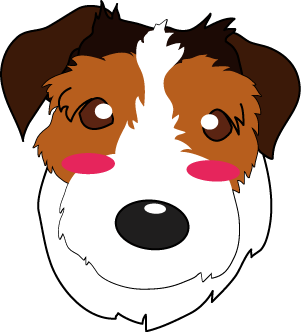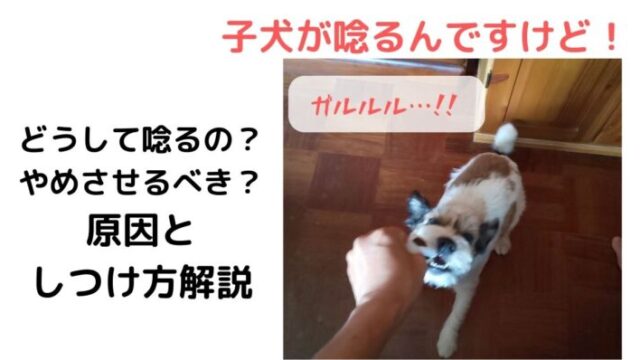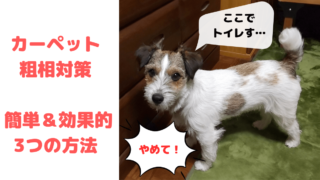子犬の夜鳴き・朝鳴き対策は安眠させる環境づくりが基本です。
- 犬が安心して眠れる状況を作る
- 運動や陽の光を浴びる散歩を十分にする
- 早起きされない工夫をする
これらの対策の中から、子犬の性格や家庭環境に合わせた対策をすれば問題ありません。子犬の成長とともに睡眠パターンも安定してきて、変な時間に鳴かなくなります。
しかし「子犬が夜中や朝に鳴いて困る」「なかなか鳴き止まなくて近所迷惑になってしまう」など子犬が寝てくれない問題は深刻です。
飼い方に問題がなければ成長とともになくなるとはいえ、今現在鳴き声で近所迷惑にならないか心配な状態で、子犬の成長を待てない方も多いでしょう。
今すぐ直したい場合の対策方法は2つあります。
- 子犬が起きないように生活を工夫する
- 飼い主の近くで寝かせて、子犬が起きるたびに相手をする
2番の方法は体力的にきついのと、寝室で一緒に寝られる環境の家庭であることなど、実施にはデメリットや条件もあります。誰でもできる方法ではないので無理にやらなくても大丈夫です。
この記事では、飼い主の視点・経験をもとに、子犬の夜鳴き・朝鳴き対策について実際の体験談も混じえて解説します。
1.子犬の夜鳴き・朝鳴き対策は子犬の性格によって変わる
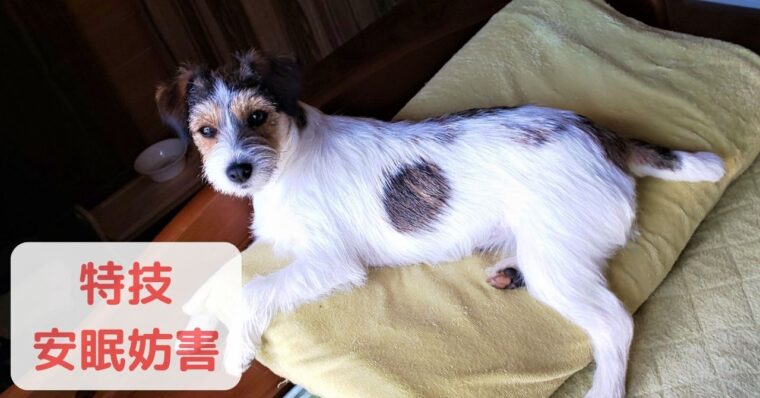
夜鳴き・朝鳴きは犬の性格によって「ほとんどない〜かなり激しい」まで大きく差があります。「かなり激しい」に該当してしまった場合は、基本通りの対策ではうまくいかないことが多いです。
子犬はどの子もよく寝ると思われがちです。しかし眠りが浅くなかなか寝つけない子犬も普通にいます。愛犬のラファは眠りが浅いタイプで、夜に頻繁に起きて寂しいからと飼い主を呼ぶ迷惑な子犬でした。
最初の2夜くらいは様子見で別の部屋でクレートに寝かせましたが、夜中に何度も起きてトイレをしたり、暴れて鳴いたりしました。
そのため最初の2週間くらいは夜中や朝にラファが起きると私も一緒に起きて、トイレなどの世話をしてまた寝かしつけるという生活を送りました。犬が起きた気配がわかるように、また寝かしつけをやりやすいように、私の寝室にスペースを作って一緒に寝ます。
私の部屋にクレートとサークルを設置し、深夜〜早朝の間に2回ほど起きて面倒を見ました。1回の時間は15分程度ですが、昼間働いているのに夜中に起きるのはしんどいです。
逆に先代犬のバロンは夜鳴き・朝鳴きがほとんどない犬だったため、対策はせず落ち着ける寝床を用意するだけ。初日から1歳くらいまでは別々の部屋で寝ていました。
その後は冬の寒い時期だけ一緒に寝て、夏は別々に寝るという生活を送りました。老犬になり介護が必要になってから看取るまでの半年間は、夜はそばで見守りながら寝ましたね。
このように同じ飼い主が同じように飼っても犬の反応は全く違います。飼いやすさも犬の個性に大きく左右されるため、思い悩まないようにしましょう。
2.【夜鳴き・朝鳴きの原因】深夜・早朝に鳴く原因と対策5種類
子犬が深夜や早朝に起き出してきて鳴くのは、犬の本能や生理現象に基づく自然な活動です。また月齢の低すぎる幼犬を迎えると、夜鳴き朝鳴きがひどくなる傾向があります。
- 月齢が低すぎる(生後90日未満)
- 運動不足でエネルギーがあまっている
- 基本的に犬は人間より早起き
- 視界が開けている
- 好みの寝場所ではない
2-1.【幼すぎる子犬】成長を待ちつつ近くで寝るか徹底的に無視する
生後90日未満の幼犬の場合は、夜中にトイレで起きたり、空腹で目が覚めてしまったります。その時にさまざまな理由で鳴いて飼い主を呼びます。
- 周りに誰もいなくて不安
- 寝床から出てトイレに行きたい
- ご飯が欲しい
- 暇なのでかまってほしい
低月齢の子犬の場合は、飼い主も夜中に起きて子犬の世話をするのが望ましいです。
本来であれば生後90日未満の子犬期は、ブリーダーの元で母犬や兄弟犬と過ごしている期間です。子犬は目が覚めたら母犬に世話をしてもらえたり、近くの兄弟犬が寝ているのを見て安心してまた寝ます。
- 飼い主も夜中に起きて世話をする
- 子犬が諦めるまで徹底的に無視
早い時期に母犬や兄弟犬と引き離されて飼い主のもとに来た子犬の場合、飼い主がある程度の期間を母犬のように見守ってあげなければなりません。低月齢の犬を迎えたら高確率で夜中の世話が必要になります。
できない場合は徹底的に無視をします。どんなに子犬が鳴いても一切無視して、絶対に子犬の様子を見てはいけません。
1回でも鳴いている子犬に反応してしてしまうとアウトです。絶対に100%無視し続けてください。どんなに鳴いても反応がないとわかると、やがて子犬は鳴くのを止めます。
無視は覚悟と飼い主の図太さも必要です。私は子犬の鳴き声が気に障って自分が寝られなくて無視できなかったです。そのため夜中に起きて世話をする方を選び、成長を待ちました。
2-2.【運動不足は大敵】日中にたくさん散歩や運動をさせて、夜ぐっすり寝られるようにする
- 午前中に外に連れ出す散歩をする
- 運動や遊びの量を増やす
- 寝る前に遊びを取り入れエネルギーを発散させる
子犬の夜鳴き・朝鳴きの原因の1つに日中の刺激不足があります。日中に外に連れ出して太陽の光を浴びさせる散歩はすごく重要です。ワクチンが終了していなくても、カートやキャリーを利用して必ず散歩をさせます。
朝(午前中)に十分太陽光を浴びると、メラトニンが分泌されて安定した睡眠に繋がります。なるべく午前中に十分に外に連れ出しましょう。
共働きなどで日中に長く留守番していると、昼間にたっぷり寝たため、夜に目が冴えてしまうこともあります。この場合は信頼できる人に日中の世話を頼み、昼間の寝すぎを防止することも有効です。
活発な子犬は散歩だけでは運動不足です。走ったり頭を使う遊びも取り入れないと疲れてくれません。
ボール投げや引っ張りっこなどでよく遊んであげましょう。就寝前にしっかりエネルギーを発散させるのが子犬を安眠させるコツです。
子犬に効果的な遊び方は以下の記事で紹介していますので、参考にしてください。
【関連記事】「引っ張りっこ」で犬と遊ぼう! 絆を深めてストレスを解消する遊び方
2-3.【犬は基本的に早起き】朝は遅くまで寝かせたい家庭は遮光するなど工夫をしよう
犬は「薄明薄暮性動物(はくめいはくぼせいどうぶつ:朝や夕方の薄暗い時間帯に活発に行動する動物のこと)」に分類されます。そのため夜明け前、朝の気配がしてくる薄暗い時間帯には起き出します。
子犬に空が明るくなってきたのを悟らせないことで、犬が起き出す時間を遅くできます。また夜はなるべく遅めに寝かしつけて、朝寝坊させるように生活させれば、深夜・早朝の吠えを防止できます。
- 1級遮光カーテンや雨戸を閉める
- 窓のない部屋や家の中心部で寝かせる
- 犬に夜更かしさせる
群れで行動する犬は、自分が起きれば群れのメンバーを起こして活動を始めます。冬はともかく夜明けが早い5〜9月頃は、犬の本能にしたがって行動されてしまうと人間は迷惑です。
人間が先に起きる生活リズムにすれば朝鳴きがなくなります。犬が人間の生活時間に合わせられるように、生活環境を整えるなどの工夫をしましょう。
完全に本能が消せず朝に鳴いてしまう場合は、自己サマータイムの導入を検討してもいいですね。
2-4.クレートは小さめの物で、視界をさえぎることが正解
視界がひらけていることも子犬の夜鳴き・朝鳴きの原因です。寝床が周囲から丸見えではありませんか?
犬は基本的に周囲から隠れることができる、狭くて暗い場所にこもって寝ることを好みます。子犬がよく寝られるようにクレートを利用しましょう。
クレートのサイズは子犬がギリギリ寝られる大きさです。大きい場合は奥にバスタオルなどを詰めて中のサイズを小さくします。
- ケージは使わない
- トイレトレーニング中はサークル併用
周囲から丸見えのケージ(金網のケージ)では、子犬は落ち着いて寝られません。すでに購入してしまっているのなら、周囲が見えないようにバスタオルやブランケットなどでケージを覆ってしまいます。
夜中にトイレに自力で行ってもらいたい場合には、クレートとトイレトレーが入るサイズのサークルを利用します。
2-5.好みのベッドや場所を提供してあげよう
- どこで寝るのが落ち着くか
- どんな寝床が好きか
- 眠りが深いタイプか浅いタイプか
夜鳴き・朝鳴きの防止には、犬がお気に入りの寝床で安眠できるようにすることも大事です。
柔らかくゆったりめのベッドが好きな犬、硬めで小さいベッドを好むなど、犬によって寝床の好みが違います。
寝る場所も、家族の近くがいい犬、1匹で寝たい犬、飼い主にくっついて寝るのが好きな犬と個性もさまざまです。
眠りが浅いタイプか深くよく眠るタイプかでも、夜鳴き・朝鳴きの度合いが違ってきます。眠りの浅いタイプは家族が見える位置で寝るほうが、起きたときの不安な気持ちが減ります。
よく観察して睡眠のタイプに合った寝床を提供してください。
4.子犬を上手に寝かしつけよう
子犬の夜鳴き・朝鳴きは近所迷惑にもなりかねない問題です。飼い主の睡眠不足を招く恐れもあるため、早期に適切な対処が必要です。
- 午前中に散歩して太陽光を浴びよう
- 運動・あそびをたくさんしよう
- 落ち着く寝床を用意しよう
- 雨戸などで朝を感じさせない工夫をしよう
- 夜更かしをさせるのもあり
工夫しても夜鳴き・朝鳴きが解決しない場合は1人で悩まずに、獣医師やドッグトレーナーに相談して解決しましょう。